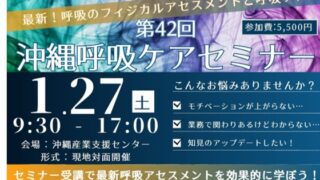脳卒中の急性期リハビリと自動車運転支援について

日本は高齢化に伴い75歳以上の免許保有者の増加であったり、
脳卒中を発症した運転者の重大事故に伴う道路交通法改正などがニュースになっています。
そんな潮流の中で,リハビリスタッフが脳卒中患者さんの運転適性評価や再開支援を行う機会が増えてきています。
今回は自動車運転とリハビリテーションをテーマに記載していきたいと思います!
急性期リハビリテーションの特徴
皆さんは、急性期病院のリハビリってどういうイメージでしょうか?
よく言われているのが、とにかく「リスク管理」が大事であると言われています。
特に脳卒中急性期の患者さんの初期介入や離床時には、、、
「Vitalsignは大丈夫かな?」
「麻痺の進行はどうだろう?」
「意識レベルは変わりないかな?」
と言った具合に、症状の変動が激しい時期ではあるので、常に評価とアプローチが一体です。そのベースとなっているのがリスク管理になります。
そんな、病気の発症からできる限り早い段階でリハビリテーションを行います!!
自動車運転のサポートの対象となる患者さんとは?
当院は350床程度の急性期総合病院であり、その平均の在院日数は約10日くらいです。
そんな患者さんの経過と転帰先もさまざまです。

だいたいは3パターンになりまして、、、
脳卒中を発症して経過が良好であれば、自宅退院となります。
しかし、運動麻痺や高次脳機能障害などの後遺症が残れば回復期リハビリ病院や療養型の病院に転院となります。
また、ご高齢であり緩やかにリハビリをしながらの自宅退院を目指す患者さんは、老健と言われる施設に入ることもあります。
例えば、軽い脳梗塞となり、特に後遺症もなく点滴加療だけて経過した場合、、、
入院してから退院まで、どのくらいの期間だとおもいますか??

この場合、おおよそ1週間程度で退院することもあります!!
意外と早いですよね!?
これまでの当院の状況
これまで、脳卒中を発症し当院入院後、自動車運転再開のニーズがあったものの、その評価方法や運転再開に関しての判断基準に統一性がない状況でした。
つまり、、、
各療法士や担当者間で適宜対応していた状況でした!!
そんなこんなで、
主治医から 「退院後すぐの運転は控えましょう」と言われたり、、、
主治医やリハビリの担当者に聞いてみても答えは曖昧だったり、、
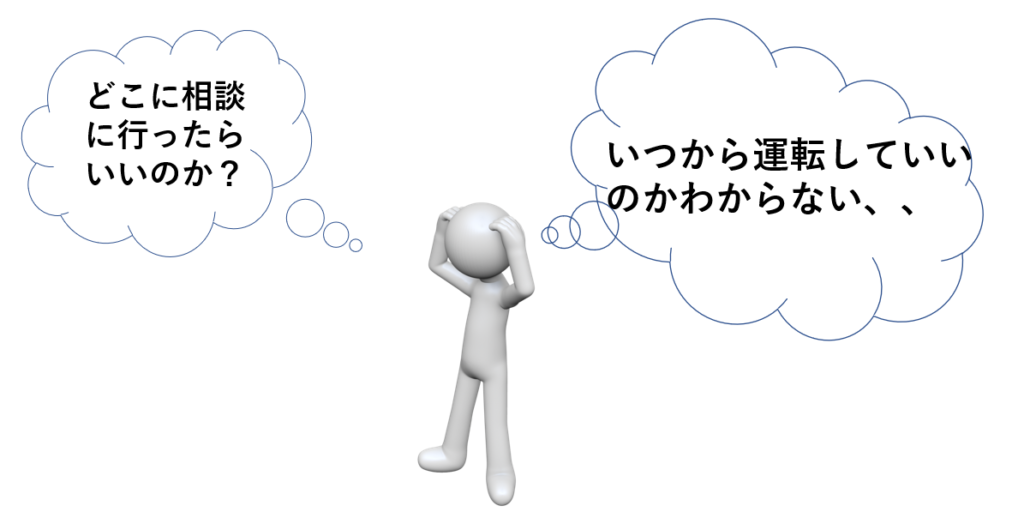
という具合で、患者さんは困っていました。。。
自動車運転サポートチームを結成!!
そんな問題を改善するため、2019年4月に作業療法士と言語聴覚士を中心に自動車運転サポートチームを結成しました!
さまざまな問題が多かったので、チームとして取り組んだこととしては、、、
・入院してからの支援の流れを可視化したフローチャートの作成
・リハビリ評価基準の策定
・関係部署との調整、連携、周知
・自動車教習所への情報提供書(サマリー)の作成
・リハビリ部署内での勉強会の開催
などなどです!
「運用マニュアルを考案し各療法士が同じレベルで支援が行えるように基盤の形成」を目指しました!
今では試行錯誤を重ねることで、それなりに運用できてきています。
次回には、当院の自動車運転支援、サポートチームを結成してのマネジメントを紹介していきたいと思います!
ではまた

自動車運転支援、サポートの体制づくりは、マネジメントが必要でした~
その際に参考となった書籍です!